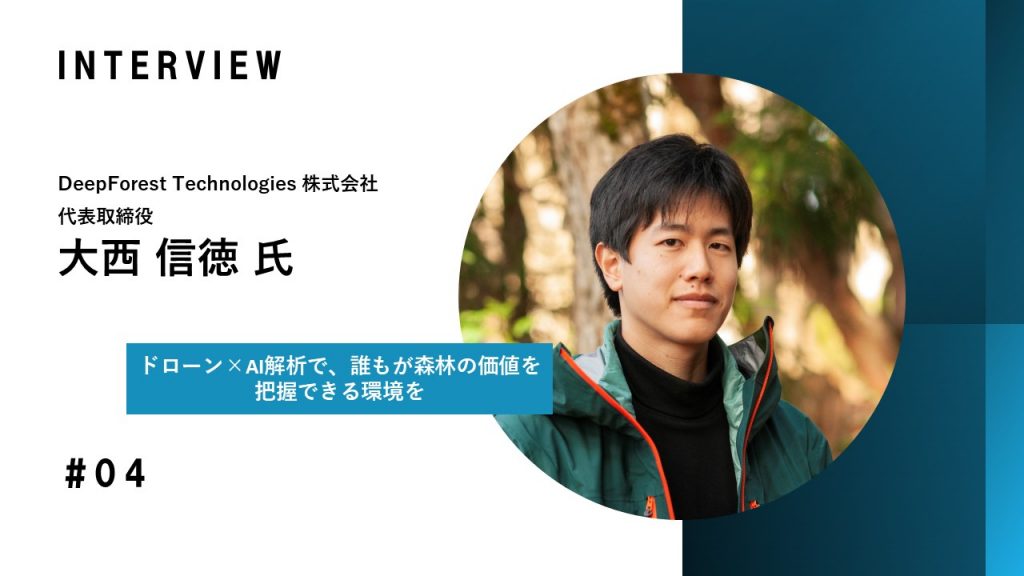
■会社説明
ドローンから森林の情報や価値を可視化する技術を開発する京都大学発スタートアップ。
AIを活用した世界最先端の技術開発を行い、精度高く森林の情報を解析する技術を開発し、ソフトウェアとして提供。日本各地での森林管理やカーボンクレジットの創出事業などに利用され、森林保全や森林管理の効率化などに貢献する事業を行っている。
(DeepForest Technologies 株式会社:https://deepforest-tech.co.jp/)
■大西信徳:
1994年生まれ。
・2013年京都大学農学部森林科学科入学
・2022年京都大学大学院農学研究科森林科学専攻博士課程修了
2025年3月14日のインタビュー記事です
自己紹介
大西:大西信徳です。京都大学農学部森林科学科の博士課程を卒業後、研究内容の事業化に向けて、会社を立ち上げて、今年で4年目になります。
また、京都大学の博士研究員(ポスドク)としても研究を続けています。もともと地球温暖化や熱帯雨林の伐採といった社会課題への関心が高く、農学部に入ったら研究で何かアプローチできるのではと思って入りました。
発表論文にニーズを感じ、起業家の道へ
幸田:大学での研究から起業という選択は、どういう流れだったのでしょうか。
大西:修士1年の時、ドローンから木の種類を識別できる技術を論文発表したところ、研究者や民間企業からたくさんの関心を寄せていただき、ニーズを実感しました。
これを契機に研究者になるよりもそうしたサービスを提供していきたいという思いが芽生え、博士3年の時に京都大学のインキュベーションプログラムに採択いただきました。
そして事業化の支援を受け、卒業のタイミングである程度プロダクトができたので、ビジネスに舵を切りました。
幸田:研究と事業の概要をご説明いただけますか。
大西:研究テーマは、ドローンから森林の情報を細かく分析する技術の開発で、撮影したデータからAIを使って木の種類を判別するというものです。
木の種類は、森林の状況を把握するのに非常に重要な情報で、スギ・ヒノキだけでも木材としての価値は変わりますし、CO₂の吸収量の計算には木の種類の情報が必要です。
会社の事業のうち、一つはドローンで撮影したデータから木の種類をAI が自動で判定するソフトウェアを提供しています。木の高さやCO₂蓄積量などの細かい情報も木一本単位で解析することが可能です。
また、実際にドローンを飛ばして解析してほしいという依頼もありますので、ドローンで計測し森林の中を調査することを行っており、最近ではカーボンクレジット、特にJクレジットに関する森林のモニタリングなども行っています。
幸田:研究の時はドローンが普及していく時代だったと思いますが、他の方も、そのようなことに同様のテーマでチャレンジはされていたのでしょうか。
大西:私が研究を始めた時は誰でもドローンが使えるようになり、ドローンを使った研究がチラホラ出てきたタイミングでした。
当時、木の高さや1本ずつ検出することはできていましたが、木の種類はAIを組み合わせればできるだろうと言われていてもまだ誰もできていませんでした。
森林における検出の実装の難しさは、木1本の範囲や種類などのデータ収集や分析手法の難易度が高いことです。私の研究ではこれまでリモートセンシングで使われてきた技術と融合させる形で、AI を組み合わせることで木1 本単位で木の種類まで判別できる技術を確立できたことが、新規性の高さにつながったと考えています。
幸田:足元、VCからも資金調達しこれから成長していくステージにあると思いますが、市場におけるポジションや今後の事業展開についてお話しいただけますか。
大西:事業の現状は、市場としてJクレジットが盛り上がってきていますが、モニタリングの技術を持っている会社がかなり少なくて、たくさんの依頼をいただいています。
ソフトウェアに関しては、ある程度しっかりとしたプロダクトができているので、日本各地で多くのユーザー獲得に向けて動いています。
今後の展望としては、海外を強化するということで、ボランタリークレジットや二国間クレジット、また、ソフトウェアも各地域で広げていくことを大きな目標としています。
幸田:今の段階で会社の課題は何かありますか。
大西:一つはソフトウェアの強化で、販路を増やすことと、現場の人が求めるものにすることが必要だと考えています。当初は自分がいいと思うものを作っていたのですが、現場ニーズをもっとしっかり聞いて使いやすくしないと売れない、ということでちょっと反省しています。
人材面ではエンジニアが非常につかまりにくい状況が続いています。ベンチャーの魅力の一つとして、私たちであれば社会貢献などがあるのですが、エンジニアの方達は、今結構引く手あまたなので、条件がいいところを優先しているようで、採用難に課題感を持っています。
幸田:今おっしゃったエンジニアの方は、どういう分野でのスキルや能力を想定しているのですか。
大西:Web周りやソフトウェアのプログラミングですね。一定の知識があって物も作っていけるエンジニアがいいのですが、国内では多くはいません。結構外国の方が多い状況だと思います。
幸田:日本の人材は育っていないという状況でしょうか。
大西:育っていないわけではありませんが、やはり海外の方が力が入っているとすごく感じます。インドやバングラデシュでは大学でしっかりと基礎を抑えている一方、日本の大企業のエンジニアは新しい技術をすぐに導入して動くことはあまりなく、採用として少し難しいと感じるところはあります。
森林の分野は、プログラミングができて解析できる人は日本人には特に少ない印象です。ですから中国など海外の方が来たりします。大学の研究力は中国や他の国に比べると弱い状況であると感じます。
幸田:最近、「日本の大学の研究力が落ちてきているのでは?」と言われることも増えていますが、研究力やポスドクなどの課題についてどのように感じていますか。
大西:実感として状況はあまり良くないと当時から感じていました。博士に進むことのメリットが正直感じられなくて、特に私達がいた農学森林の分野では博士に行ってその後どこ行くのか?という状況でした。
資金面では、博士に進んでも学振(学術振興会特別研究員制度)の採択率が3割程度なので、通らない人の中には博士をやめる人も実際いました。博士を出た後に用意されているポジションの少なさにも痛感しました。
ですから、私が修士で研究室に入ったとき、森林以外の分野でも使える技術をつけようと思い、プログラミングという技術を身につけて、結果的にその技術と森林が合わさって非常にいい研究結果が得られました。
ミッションは、未来の地球を支える技術を作ること
幸田:起業して4年経たれて、楽しさも苦しさもいろいろある気がしますが、その辺りはどんな感じですか。
大西:充実していると思っていますし、自分の立場の考え方で言うと、やりたい研究をいろんな人にサポートしてもらいながら続けられているので、一種の研究者としての楽しみも感じています。
辛いところでは、うまくいかないことは山ほどあります。採用しても会社やメンバーと合わないで辞めていったり、実際にいいプロダクトと思ったものでもあまり売れなかったりします。
いろいろありますが、それでも価値があることを進んで、自分の選択ができているところはやっぱりいい道というか、いい人生を歩んでいるだろうな、という胸を張って言えるとは思います。
幸田:会社のミッションについて教えてもらえますか。
大西:ミッションとして未来の地球を支える技術を作ることが一つあるのですが、やっぱり技術ですね。他の真似ではなく新しい森林保全の技術を作って、それが未来を支えていく、そういったところを大事にしています。
幸田:最近、岩手県の大船渡で大規模な山林火災がありましたが、どう捉えていますか。
大西:あれだけの災害ですし、しばらくは燃えてしまったという話が中心になると思います。ただ、本当にやるべきことは、元々どういうところが燃えてどうなったのか?ということを見ないといけません。
例えば排出されたCO₂の量の算出などをする、ということも考えた方がいいと思います。
自分たちの技術で森林保全された実績をもっと増やしたい
幸田:今後の取り組みについて、一言コメントいただければと思います。
大西:まだ私達の技術で世の中のここが良くなったところは少ないので、私達の技術があったからこの森林は保全されたという事例をもっともっと増やそうと考えています。
そのために技術開発だけでなく、今後は世界の色んな国に行って、様々な森林の現状を実際に知って、そこで何ができるかを一つずつしっかりと見て対応していこうと思っています。
東南アジア、アマゾン、アフリカを特に重要なターゲットと捉えています。
幸田:ぜひ頑張って取り組んでいただければと思います。
大西:本日はありがとうございました。
(了)

